経営・管理ビザ更新時の「経営改善の見通し評価書」とは何か?作成方法も!
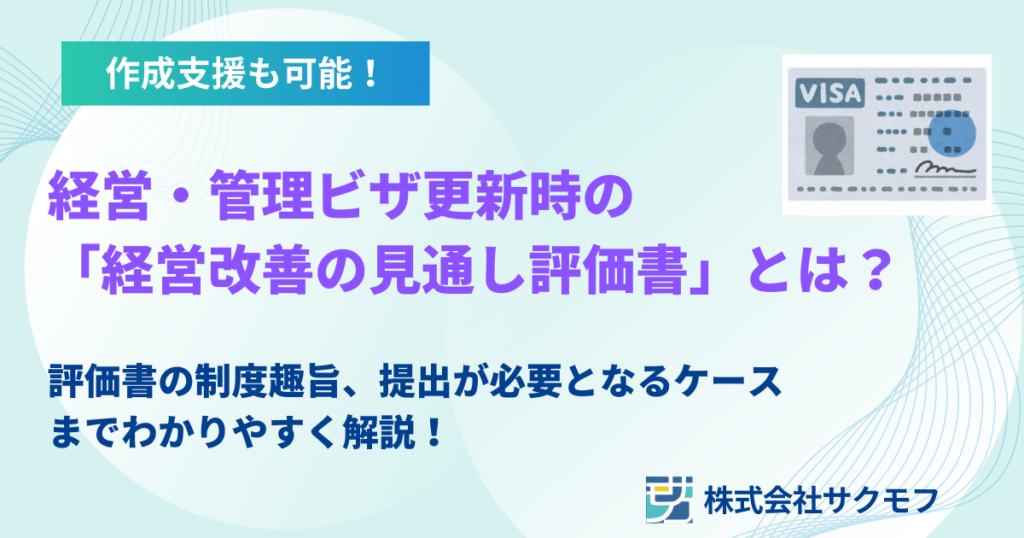
みなさん、こんにちは。
外国人が日本で会社を設立して事業の経営を行う際等に必要となる「経営・管理ビザ」は、ビザ取得後も事業の継続性や安定性が審査されます。
そして、業績が振るわない場合には、ビザ更新時に「経営改善の見通し評価書」という書類の提出を求められることがあります。
本記事では、経営・管理ビザの概要から経営改善の見通し評価書の制度趣旨、提出が必要となるケース、作成者と作成プロセス、外国人経営者が注意すべきポイントまで、専門的かつ丁寧に解説します。
外国人経営者ご本人はもちろん、それをサポートする行政書士の方にも有益な情報となっているかと思います。ぜひご参考ください。
また、当社では「経営改善の見通し評価書作成支援サービス」を提供しています。
無料相談も受け付けておりますので、興味のある方は気軽にお問い合わせください。
\「経営改善の見通し評価書」を迅速作成!/
目次
「経営・管理ビザ」とは何か
経営・管理ビザの概要
経営・管理ビザとは、日本で事業の経営を行ったり事業の管理に従事したりする外国人に与えられる就労ビザです。その活動内容は「本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動」であり、一定の条件を満たす場合に在留が認められます。
かつては「投資・経営ビザ」と呼ばれていましたが、2015年の入管法改正により「経営・管理ビザ」として制度整備されました。
本在留資格の目的は、外国人による企業経営や起業活動を促進しつつ、日本国内で安定的かつ継続的に事業が行われるようにすることにあります。
経営・管理ビザの要件
経営管理ビザを取得・維持するためには、法律で定められた要件を満たす必要があります。主な要件として以下が挙げられます。
- 事業所の確保:日本国内に事業を行うための事業所(オフィスや店舗)が存在していること(事業開始前でも事業所として使用する施設を確保している必要あり)
- 事業の規模要件:事業の規模が十分であること。具体的には、常勤の従業員が2名以上いるか、資本金または出資金が500万円以上であること、あるいはそれらに準ずる規模であること
- 経営の継続性・安定性:事業計画の適正さや財務の安定性、継続性を示すこと(特に、新規ビザ申請時には事業計画書などで事業の将来性や収支見込みを提示し、事業が適正に運営され継続可能であることを証明する必要あり)
- 経営への実従事:申請者本人が実際にその事業の経営または管理業務に携わっていること(名義上の経営者で実態は他者任せという場合は認められない。また、会社の管理者(雇われ社長等)としてビザを取得する場合には、経営・管理について3年以上の実務経験や日本人と同等以上の報酬が必要になるなど追加要件がある)
以上のように経営管理ビザは日本で安定した事業運営を継続することを前提に許可される在留資格です。初回の在留期間は通常1年程度であり、その後事業が順調に継続・成長していれば3年や5年への延長も可能です
逆に言えば、事業の不振や継続性への懸念がある場合、ビザの更新が許可されないリスクがあります。こうした中で設けられたのが「経営改善の見通し評価書」を提出させる仕組みであり、一時的な業績不振でも合理的な改善計画があれば在留継続を認めるための救済策とも言えます。
「経営改善の見通し評価書」とは何か
経営改善の見通し評価書とは、中小企業診断士等の公的資格を持つ第三者(専門家)が、申請企業の財務状況や事業計画を分析し、今後事業が改善する見込みがあるかを客観的に評価したものです。経営・管理ビザの更新審査において提出が求められることがあります。
制度の趣旨としては、業績不振に陥った外国人経営者の事業について「本当に立て直し可能かどうか」を専門家の視点で見極め、事業継続の可否を適切に判断するために導入されています。「経営改善の見通し評価書」の目的は、入管当局が公表しているガイドライン「外国人経営者の在留資格基準の明確化」の中で明示されています
近時の経営状況が悪化している場合においても、合理的な改善計画があり1年以内に財務状況が健全化する見通しが立つのであれば、事業の継続性を認めてビザ更新を許可しようというのが「経営改善の見通しの評価書」制度の背景となっています。
「経営改善の見通し評価書」は経営管理ビザ更新時の重要書類の一つであり、特に「債務超過の状態が続いている場合」には提出が事実上必須となっています。
「経営改善の見通し評価書」はどのような場合に提出が必要なのか
「経営改善の見通し評価書」の提出が求められるのは、主に経営・管理ビザ更新時に事業の継続性に疑義が生じる場合です。具体的には、会社の財務状況が悪化しているケースや事業実態に不安があるケースで入管当局が評価書の提出を求めます。
以下に典型的な事例を挙げます。
- 直近決算が赤字で債務超過に陥っている場合:最新の決算期で大きな損失を計上し、累積の損失が資本金を上回って会社の純資産がマイナス(債務超過)になったケースです。この場合、通常のままでは「事業継続性が認めがたい」と判断されるため、赤字の原因と具体的な改善策、そして1年以内に債務超過を解消できる見込みを示した評価書の提出が必要になります。もし適切な改善計画が示せない場合、在留期間の更新は許可されない可能性が高まります。逆に、専門家の評価書により「今期中に債務超過を解消できる」と合理的に説明できれば、更新許可が下りる余地が生まれます。
- 直近決算が赤字だが債務超過には至っていない場合:最新期に損失を出したものの、会社の自己資本(剰余金)がまだプラスで債務超過は免れているケースです。この場合は事業継続性が直ちに否定されるわけではありませんが、入管局から今後1年の事業計画書や収支予測の提出を求められることがあります。提出資料を精査した結果、改善の見通しに不安が残る場合には、さらに専門家による評価書の提出を追加で求められるケースもあります。要するに、「単年赤字だがまだ資本が残っている」状況では、基本的には継続性ありとしつつも、将来計画の説明責任を果たす必要があるということです。実際に評価書提出まで求められるかは状況次第ですが、赤字の原因分析と具体的な改善策の提示が求められる点は共通しています。
- 2期連続で債務超過となっている場合:前期末と直近期末の両方で債務超過(2期連続の純資産マイナス)が確認されるケースです。この場合、1年以上にわたり深刻な財務不健全状態が続いており、十分な改善がなされなかったと見做されます。入管のガイドライン上も「原則として事業の継続性が認められない」(ビザ更新不許可の可能性が極めて高い)と位置付けられています。つまり評価書の提出以前に、経営・管理ビザの存続自体が極めて難しい状況です。この段階では増資や事業再生など抜本的な対策を講じない限り、ビザ更新は認められないでしょう。したがって、債務超過が2期続く前に早期に対策を打ち、必要に応じて評価書を準備することが肝要です。
ただし、2期連続で債務超過となっている場合でも、当該企業が新興企業(設立5年以内の国内非上場企業)であれば、「経営改善の見通し評価書」を提出し、債務超過となっていることについて合理的な理由があると判断されれれば、経営・管理ビザの更新が認められることがあります。 - 売上が極端に低い、または事業実態が乏しい場合:財務上の赤字・債務超過でなくても、そもそも売上高がほとんど無い場合も注意が必要です。例えば、直近決算までの2期間連続で売上総利益(粗利)がゼロのような場合は、「実質的に事業を行っていない」と判断され、事業継続性がないとして更新が不許可となる恐れがあります。実際、売上高がゼロの会社では入管から厳しく事情を問われ、必要に応じて専門家の評価書提出や追加資料の要求がなされます。つまり、事業を動かしていない(利益を生んでいない)状態もまたビザ継続のリスク要因であり、その改善策の説明が求められるのです。
以上が主なケースですが、総じて言えるのは「事業の安定性・継続性に疑義があると入管が判断した場合」に「経営改善の見通し評価書」の提出が必要になるということです。
これは更新申請者に対し、事業の将来見通しについて専門家の裏付けを求めることで、的確な審査を行うための措置です。したがって、外国人経営者の方は決算内容に注意を払い、赤字や債務超過となりそうなときは早めに専門家へ相談して対策を準備することが望ましいでしょう。
「経営改善の見通し評価書」は誰が・どうやって作成するのか
経営改善の見通し評価書は、専門的な資格を持つ第三者によって作成されなければなりません。
具体的には、中小企業診断士(経営コンサルタントの国家資格)、公認会計士といった、「企業評価を行う能力がある」と公式に認められた有資格者が作成者となります。(自社の社員や関係者が勝手に書いた計画書では代替できないこととなっています)
評価書作成のプロセスは以下のようなステップで進みます:
- 専門家への依頼:まず、会社(またはサポートする行政書士)は中小企業診断士などの専門家に評価書作成を依頼します。事業内容や財務状況に通じた専門家を選定することが望ましいでしょう。依頼を受けた専門家は、ヒアリングの日程や必要資料のリストを提示します。
- 現状分析とヒアリング:専門家は会社の最新の決算書類(貸借対照表・損益計算書など)や事業報告書を入手し、経営状況を分析します。同時に経営者へのヒアリングを行い、赤字・債務超過に陥った原因や背景、現在までに講じている対策、今後のビジネス戦略などについて詳しく聞き取ります。例えば「主要取引先の倒産による売上減少」「新製品開発の先行投資で費用計上が嵩んだ」等、状況によって様々な要因が考えられます。それらを整理しつつ、経営者が考える改善策(コスト削減計画、新市場開拓計画、追加資金調達など)を共有します。
- 事業計画書・収益予測の作成支援:評価書を作成する上で基礎となるのが、今後の事業計画書および収支予測です。専門家は経営者と協力して、向こう1年~数年の具体的な事業計画を策定します。計画書には事業概要・市場環境・マーケティング戦略・収益モデル・コスト見直し策などを盛り込み、数字面では売上予測と費用見積もりを詳細に算出します。入管が重視するのはこの計画の現実性と具体性であるため、専門家は市場データや過去実績を踏まえて無理のない予測を立てることに注力します。例えば、「来期に売上を2倍に伸ばす」といった楽観的すぎる計画では説得力に欠けるため、根拠となる契約予定や受注見込みがある場合のみ盛り込む、といった形で慎重に数字を積み上げます。場合によっては、黒字転換を確実にするため追加の資本注入(増資)や融資についても検討し、その計画も織り込んでいきます。
- 経営改善の見通し評価書の作成:上記の分析と計画を踏まえ、専門家が経営改善の見通し評価書を作成します。評価書の一般的な構成は、①事業概要(会社の事業内容・経営者プロフィール等)、②現状の経営課題(財務状況や赤字・債務超過の原因分析)、③改善計画の内容(具体的施策と実施スケジュール)、④将来収支の見通し(損益予測・資金繰り見込)、そして⑤専門家の評価意見(計画の実現可能性評価と結論)といった項目です。特に重要なのは⑤の部分で、専門家として「○○の施策により1年以内に債務超過を解消できる見込みである」「計画達成の根拠として△△の契約がすでに締結済みである」といった具体的な評価コメントを記載します。入管当局はこの評価コメントを重視し、改善見通しの信憑性を判断します。評価書には数字データ(予測PLやBSの推移表など)を添付するほか、評価の根拠となる資料(契約書や発注書の写し、業界統計資料 等)があれば適宜添付します。
- 最終確認と提出:完成した評価書の内容を会社側(経営者や行政書士)と共有し、事実誤認がないか、計画に無理がないか最終確認し、入管に提出します。評価書には作成日付や専門家資格名も明記されます。なお、日本語で作成されるのが通常ですが、外国人経営者向けに英訳を添えるケースもあります(入管提出自体は日本語が原則)。
評価書作成に必要な主な資料としては、直近2期分程度の決算書類(貸借対照表・損益計算書・勘定科目明細など)、会社概要書(定款や登記簿謄本、事業内容説明資料)、現在までの営業成績資料(売上推移や主要顧客リスト)、そして今後の事業計画書・試算表などが挙げられます。場合によっては債務の内訳(借入先・金額・返済期日)や資金繰り表も求められます。専門家はこれら資料を総合的に検討したうえで評価を書くため、正確で詳細な情報提供が不可欠です。
評価書の作成には通常数週間程度を要しますが、ビザの在留期限が迫っている場合には迅速な対応も求められます。したがって、早め早めの準備と専門家への依頼が肝心です。
まとめ
いかがだったでしょうか。今回は、経営・管理ビザの更新に関連する「経営改善の見通し評価書」について、その概要から作成方法、留意点、まで詳しく解説しました。
外国人経営者にとって日本で事業を続けることは、法制度や言語の壁もあり決して容易ではありません。しかし、適切な専門家の助言を得て着実に改善策を実行していけば、事業の再生と在留資格の維持は十分可能です。本記事の内容が、皆様のビザ更新手続きと事業改善の一助になれば幸いです。
「経営改善の見通し評価書」について、「評価書を求められたが誰に相談すれば良いか分からない・・・」、「一度プロに相談してみたい」といった方はぜひ弊社のサービスを利用してみてください。
実績豊富な中小企業診断士が、貴社の状況に応じた最適な改善計画の策定と評価書作成をサポートいたします。
無料相談も受け付けておりますので、興味のある方は気軽にお問い合わせください。
\「経営改善の見通し評価書」を迅速作成!/
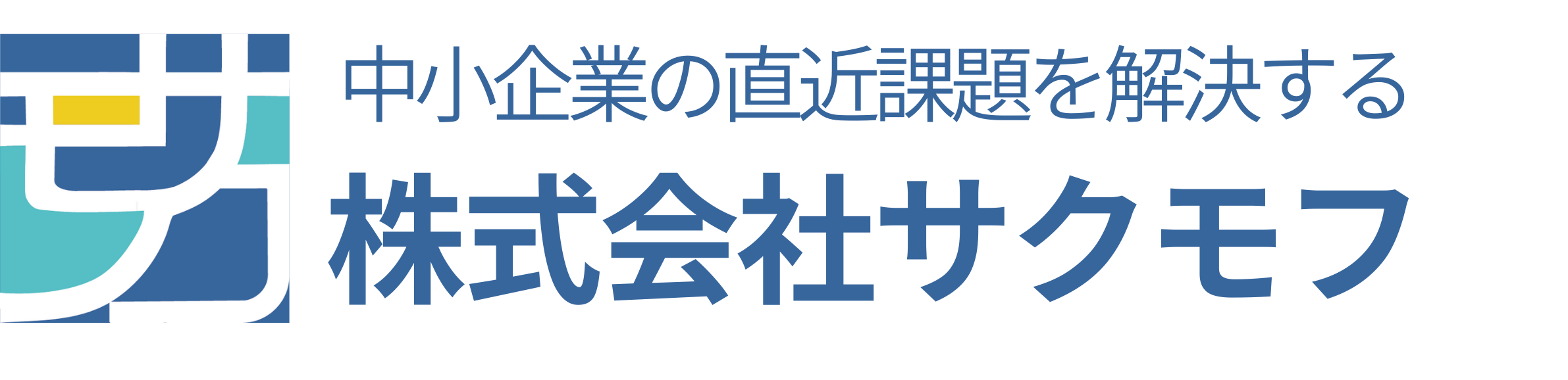
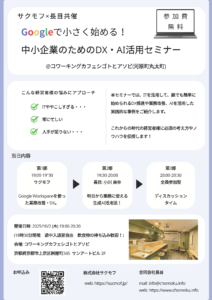
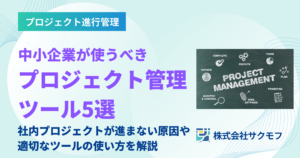
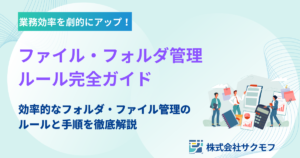

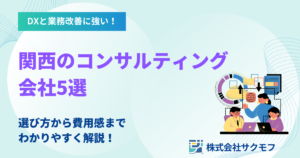
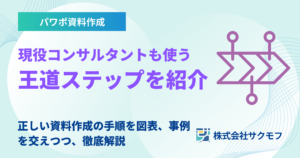
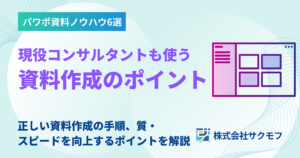
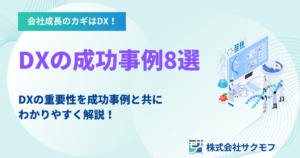
コメント